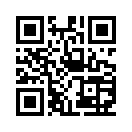地域シゴトの学校 10日目
2008年10月18日(土)
グループワークが始動したはいいのだが、一体のどの方向に歩を進めていっていいのかわからない。
「僕はこっちだと思うな~。」
「私の意見は~・・・。」
と、思っていたようにみんなそれぞれの思いをお持ちだ。
こんな事ばかりケンケンガクガクと話していたのでは会議が進まないぞ~と、やはり心配であった。
ところが!
さすがは長年地域シゴトの学校を運営してくださっているコーディネーター&サブコーディネーター並びに事務局の皆さま。
行き詰まりそうな先々にちゃ~んとその時々のスキルを与えてくださる講師の方々をコーディネートしてくださってます。
まるで神の手みたい(笑)
んなわけで、10日目の地域シゴトの学校は「会議ファシリテーターになろう」でした。
ファシリテーターとはなにか。
簡単に言えば会議の進行させる能力のこと。
その会議を前進させる役割の人をファシリテーターと呼ぶのである。
その言葉自体も、聞いたことはあるにせよどのような能力なのかまでは私も知らなかったのが本当のところ。
講師は青木 将幸 さん
地元のNPOで活躍された後、5年ほど前に独立し、 ファシリテーター事務所を立ち上げた方です。
下手な会議を上手に進行したいと感じた青木さんは、10数年前に海外においてファシリテーターとしての職業が存在することを知るきっかけとなったのだが。
そもそも日本が会議進行が上手でない理由の1つとして感じているのが、小学校時代からの経験の無さだとか。
もっともっと小学生の時分からみんなで話し合うことを担任を通じて学び、経験するべきだと言う。
最近になり徐々に増えつつあるものの、青木さん自身ももっともっと義務教育時代の学生に会議進行能力を身につけるお手伝いが出来ればとおっしゃっていました。
さて、一日かけてワークショップ形式で学ぶわけなのだが、これがまた大変で大変で。。
経験がものを言う手法ということがよ~くわかりました。
様々なテクニックが存在するのだが、それば全て当てはまるとも限らない。
会議する上で、テーブルの数、椅子、並べ方1つでまったく違った会議が進行されやすい。
といったことも、自分たちはこう感じるのだけれど、他のグループの人達はこっちの配置の方が良いとか。
そんな環境作りも、会議をスムーズに進行させる上でのテクニックだとか。
様々な進行においてのテクニックがあるにせよ、会議進行においての起承転結を伝授していただいた。
共有→拡散→混乱→収束
この起承転結をとにかく意識して私達グループは《幸せのレシピ》について会議を行った。
(スゲー壮大なタイトルだな~)(^_^;)
ファシリテーターとしておおせつかった私なのだが、数十分休憩時間があったので
「どうしようかな~。でけーテーマだな~。」
と、少々、、、、イヤ大分頭を悩ましたのだが。
まずはKJ法でみんなの「しあわせ~~♪」と感じる時を絵で2つ描いていただいた。
ある方は秋刀魚をおかずに食卓で食べているとき。
ある方はお酒を飲んでフワフワ~と良い気分になっているとき。
等々、人によって幸せと感じるときは様々。
まあ~ここまでは想像できた。
話は飛ぶが、私達グループがECOについて考えているのだが、ECOと言っても範囲が広すぎるため様々なECOの取り組むべき課題があるわけで。
そんなこんなでケンケンガクガクしているのが今我々が目の当たりにしている現状。
話を戻すが、その状況とまったく一緒なのだ。
みんなが共有できる幸せの定義が必要と感じた。
たった30分という短い会議において収束まで運ばなくてはならないため私がとった手法は
《幸せをデザインで表すとこんな形》。
先にも述べたように、変則的なKJ法を使い幸せと感じる瞬間をメンバーに絵で描いていただいたのだが、さらにその状況をデザイン(記号)に変換していただいた。
ここまでが拡散。
そのデザインを元にメンバーがケンケンガクガクと共通項はないかと意見を出し合う。
ここが混乱。
そして共通項を見いだし、1つにデザインに仕上げる。
ここが収束。
ちょっぴり時間をオーバーしてしまったがなんとか時間内に収束までたどり着けたのは、かなり自分の中でも満足できた。
だが、私が感じるファシリテーターとして一番大変だと感じるのは、ファシリテーターは会議進行上、絶対に中立の立場でいなくてはならないと言うこと。
書記が議事録を書く上で中立の立場で書記をするように、まして会議進行役も絶対に中立の立場を保持しなくてはならなければいけない。
第三者的な立場の方がファシリテーターとして進行する分にはやりやすいと思うのだが、メンバー同士におけるファシリテーターがいかに難しいか。。
この難しさは容易に想像できるだろう。
これが出来なければファシリテーターをしない方がいいとまで言われたのだから間違いない。
これから先、グループワークがますます活発に行われるのであるが、
果たしてどうなる事やら。。。
先はまだまだ長い。。
ようで短い。。