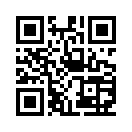講師は同次郎長通り商店街4代目当主 魚初商店の中田氏。
第1部は、清水の漁港の歴史について語っていただきました。

第2部には、清水ならではの珍味、《イルカ(海豚)》料理を食しながらの交流会。
いるかの味噌煮

ねぎすのすり身汁

「ねぎす」とは、きすに似た深海魚だそうです。
で、もっとも自分が美味しいな~と思った逸品が、いるかのたれ

塩で絞めて天日で干す、言わばいるかの干物。
お土産で少し頂いたので、酒の肴にいっぱいやっていると、4歳の娘がたいそう気に入り、妻も一口食すと
「うっ!!臭い。。」
と、返してきた。。もったいないもったいない。

消費者の魚離れがあると、噂には聞くが、実際にそれほど魚離れが進んでいるとはあまり実感がない。
焼き魚や、煮魚として食すことは少なくなっているかもしれないが、刺身として加工してある魚についてはは、回転寿司を代表するように需要はかなりある気がする。
店主の中田氏も言っておられたが、うまい魚が手に入る清水だからこそ守っていきたい食文化があり、調理法がある。中田氏も子供の頃は本当に魚が大嫌いと言っていた。が、大人になり、魚の旨さ、且つ、清水で水揚げされる魚の旨さにのめり込み今に至るという。
子供の時には「何故この旨さがお前にはわからんのじゃ~!」ではなく、こういう魚もあるし、こうした調理法もあるんだよ
ということを知ってもらうだけでもよし。
味覚はだんだんに年を重ねるごとに変わるもので、その味が分かる年令になるまで分からんでもよいとのこと。
でも、家庭で、まちで、この魚のうまい食文化を、いつの頃か旨さを知る頃になったこども達がいつでも食せるように守っていきたい。
そう語ってくれました。
いつの頃か、いるかを食す文化は衰退していくだろう。
だが、いるかを食す文化を広めたいとは決して思わない。そうとも言っていました。
同市であっても葵区に住む私にも非常に興味深い話しが満載。
まだまだ清水というまちには、掘り起こせばザクザクと出てくるお宝が満載の町だ!